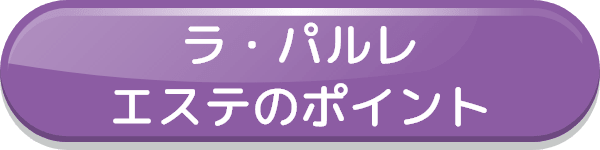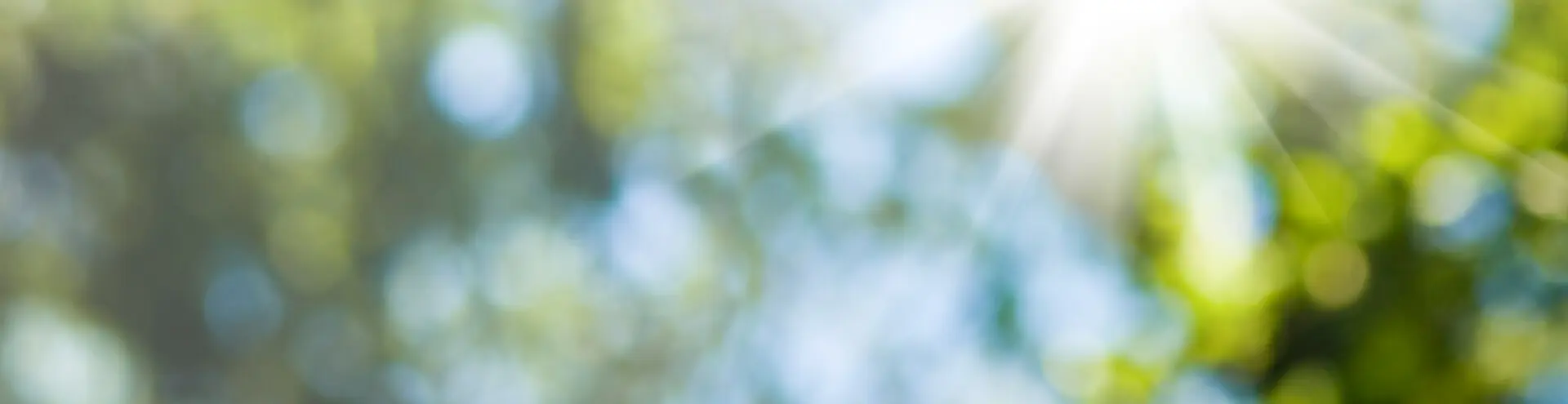健康コラム 2025.06.27
【お酒とダイエット】ダイエット中の飲酒はやっぱり太る?

ダイエット中のお酒との付き合い方について、お酒は控えるべき!やハイボールは糖質がないからたくさん飲んでも大丈夫!など様々なことが言われます。
お酒が好きな方は毎日飲むのが習慣になっていたり、お酒を飲むことがストレス解消になっていたりする場合もあります。お酒をやめることがストレスになり、それがかえって暴食に走る原因になってしまっては意味がありません。とはいえ、お酒の飲みすぎを気にせず続けていては、どんなにダイエットを頑張っても成果が得られにくく、それどころか病気や命の危険につながる可能性もあります。
また、普段1人では飲まないけれど、ダイエット中に飲みに誘われたとき、何を頼んだらよいのかわからないという方や、付き合いや接待だけでも週に何回も飲まなければならないという方もいらっしゃると思います。そんなダイエット中のお酒との付き合い方についてどんな飲み方ならOKなのか、どんなことに気を付ければよいのかをまとめていきます。
≪目次≫
お酒がダイエットでよくないとされる理由

アルコール代謝が優先されて脂肪がつきやすい
お酒に含まれる成分のうちエネルギーになるものには、主にアルコールと糖質があります。糖質は、身体にとってエネルギーを生み出すのに欠かせない栄養素ですが、摂りすぎると体脂肪として蓄積してしまう為、生活習慣病の原因にもなります。一方で、アルコールは、糖質同様にエネルギーを生じますが、糖質と異なり身体に蓄えられることのないエネルギーです。それゆえに、ハイボールは糖質がなくてエンプティカロリーだからいくら飲んでも太らない!と言われることがあります。が、そんなことはありません。
もちろん糖質の多いお酒と比べれば糖質のないハイボールのようなお酒の方が太りにくいですが、アルコールにカロリーがないわけではないので、過剰なアルコール摂取は太る原因になります。アルコールのエネルギー自体は身体に蓄積しなくても、アルコールの代謝を優先することで、他の栄養素の代謝が後回しになり、長時間体内に残存することになります。
蓄えられないアルコールのエネルギーを先に消費しようとすることで、お酒や食事・おつまみに含まれる糖質や脂質が本来より何時間も長く体内に残され、体脂肪になりやすくなるということです。
また、大量にお酒を飲むとアルコールを代謝してつくられたアセチルCoAという物質が中性脂肪として蓄えられるため、アルコールが体脂肪の蓄積に直結することもあると分かっています。
アルコールに反応して体脂肪がつきやすくなる
アルコールを摂取すると体内では中性脂肪のもとになる“脂肪酸”をつくる酵素の働きが高まり、反対に脂肪酸の燃焼をサポートする酵素の働きが抑制されると言われています。また、アルコールの代謝過程で生じるアセトアルデヒドが、中性脂肪の分解や脂肪酸の燃焼に関わる別の酵素の働きも抑制してしまうため、体脂肪がつきやすくなります。
このように、人間にはアルコールに反応して脂肪をため込みやすくする仕組みが備わっているため、太りやすくなると言われています。
筋肉が落ちる
アルコールが体内に入るとストレスホルモンとも呼ばれる“コルチゾール”というホルモンが分泌されます。コルチゾールには筋肉を分解して糖を作り出す働きがあるため、筋肉量が減少してしまうと言われています。アルコールがほんの少し体内に入っただけでも筋肉は分解されると言われています。筋肉が落ちると代謝が低下してしまうため、燃焼しにくい身体になってしまいます。
ほかにも、アルコールを摂取すると男性ホルモンである“テストステロン”の量が減少すると言われています。男性ホルモンとはいえ、女性にも存在しており、これが減少することで筋肉がつきにくくなります。さらに、筋肉合成に関わるたんぱく質キナーゼの機能が低下することにより、筋肉の合成もされにくくなります。
このような様々な理由により筋肉の分解が促されるだけでなく、筋肉の合成もされにくくなることから、筋肉が落ち、代謝が下がるため、太りやすい体質になってしまうのです。
活性酸素が増える
活性酸素は身体が酸化する原因となる物質で、簡単に言えば錆びつかせて老化を促進させる物質です。活性酸素が増加すると、血流が低下して代謝が落ちたり、老廃物の排泄が滞ったり、また美容全般でいえばシミ・しわ・たるみなどを引き起こします。
酸化してもすぐに目に見える変化にならないためおざなりになりがちですが、一度酸化が始まると連鎖反応でどんどん広がっていくため、過剰な飲酒を長年続ければ続けるほど、痩せにくい体質になってしまいます。
このように、アルコールは体脂肪がつきやすくなることや筋肉が落ちやすくなり代謝が落ちるなどの理由から、ダイエットも面では特に摂りすぎには注意したいものです。ただし、全く摂ってはいけないのではなく、うまく付き合っていけばダイエットの妨げにならずお酒を楽しむことができます。
飲酒量の目安

適正飲酒とは
適正飲酒”という言葉がありますが、実際どのくらいの量を指すのでしょうか。
厚生労働省が定める「健康日本21」では、“節度ある適切な飲酒量”は純アルコール量で20g/日程度とされています。また、「健康日本21(第二次)」の“生活習慣病のリスクを高める飲酒量”は男性は40g/日以上、女性は20g/日以上とされています。
生活習慣病のリスクを高める飲酒量は女性の方が男性よりも少なくなっていますが、これには女性の方が男性よりもアルコールの分解速度が遅いことが関係しています。女性の方がアルコールの代謝に時間がかかる分、同じ量のアルコールを摂取しても臓器障害になるリスクが高いと言われているためです。個人差もありますが、特に女性は純アルコール量で20g/日未満にしておくのが良いでしょう。
純アルコール量20gはどのくらい?
| 種類 | 度数 | 量 | 目安 |
|---|---|---|---|
| ビール | 5% | 500㎖ | 中瓶1本 |
| チューハイ | 3% | 800㎖ | 2缶 |
| チューハイ | 7% | 350㎖ | 1缶 |
| ハイボール | 9% | 250㎖ | 1杯 |
| 日本酒 | 15% | 180㎖ | 1合 |
| ワイン | 12% | 200㎖ | 2杯 |
| 梅酒 | 12% | 200㎖ | 1杯 |
| 焼酎 | 30% | 90㎖ | 1/2合 |
| ウイスキー | 40% | 60㎖ | シングル2杯 |
表は一般的なアルコール度数をもとに作成していますが、アルコール度数はものによってかなり差がありますので、より正確に知りたい方は以下の式で算出してみてください。
純アルコール量(g)=お酒の全体量×アルコール度数÷100×0.8(アルコールの比重)
毎回の飲酒量をこの量に留めることが理想ですが、飲み会などではこの量に留めるのは難しい方も多いと思います。そんな方は、1週間で140gなど期間を広げて調整してみてください。例えば金曜日に飲み会で純アルコール50gを摂ったら、土日は休肝日にして月・火・木は缶ビール1本ずつ(毎週水曜日は普段から休肝日にする)などです。もちろん1度にたくさん飲む方が健康への悪影響は大きいので、可能なら毎日適正量を守るに越したことはありません。
また余談ですが、純アルコール20gの分解には約4~5時間かかるとされています。そして40gなら8~10時間と量が増えるとともに分解にかかる時間も長くなります。たとえば飲酒してから睡眠を経て半日以上が経っていても、分解され切らない状態で車の運転などをした場合には飲酒運転にあたります。睡眠中は特にアルコールの分解が遅くなったり、体調によって普段より遅くなったりすることもあるため注意しましょう。
太りにくい飲み方5選

できるだけ糖質の少ないお酒を選ぶ
糖質のないお酒でも太る、というお話をしましたが、やはり糖質の多いお酒よりは少ないお酒の方が太りにくいです。
お酒には数々の種類がありますが、製造方法によって醸造酒、蒸留酒、混成酒に分けられます。醸造酒には日本酒、ビール、ワインなどがあり、比較的アルコール度数は低いものの糖質が多く太りやすいお酒です。飲む場合でも乾杯の1杯だけなどにとどめておくのがおすすめです。
蒸留酒にはブランデー、焼酎、ウイスキーなどがあり、醸造酒とは反対にアルコール度数は高いものの糖質が少ないため、飲みすぎなければ太りにくいお酒です。混成酒は、リキュール、ベルモット、梅酒、みりんなどで、醸造酒や蒸留酒を原料に作ったお酒を指します。アルコール度数が高く、糖質も比較的多い為ダイエットでは極力控えたいお酒です。
お酒に本来含まれている程度の糖質量であれば血糖値を急上昇させるほどにはならないため、日本酒やビール、ワインなどの糖質はまだ良いですが、梅酒やカクテル、などの甘いお酒はジュース同様、血糖値の急上昇を招くため特に控えたいものです。
一番おすすめなのはウイスキー、ハイボール、甘くないレモンサワーなどで、それが苦手だという方は、日本酒やワインを少しずつ飲むのがおすすめです。また、薄いお酒を何杯も飲んでしまうと胃液が薄まり、冷たいもので胃腸が冷え消化機能が低下してしまうため、濃いお酒をちびちび飲むのがおすすめです。
糖質や脂質の少ないおつまみを選ぶ
飲み会などで太る原因の一番の理由はお酒自体よりもおつまみの食べすぎというケースは多くあります。お酒を飲むと、体内ではアルコールの代謝が優先されて糖質や脂質の代謝が遅れるため、たくさん食べてしまうといつも以上に脂肪になりやすいです。
また、アルコールの代謝が優先されることで一時的に血糖値が低下することがあり、これが食欲の増加につながるため、普段より食事量が増える原因になるとされています。シメのラーメンやパフェなどを欲してしまうのはこのためで、ダイエット時にお酒を飲む場合には普段以上に意識的に食事量を抑えることが必要です。
おつまみとしては枝豆、冷奴、刺身、焼き鳥、トマト、きゅうりなどがおすすめです。脂質や糖質の多い唐揚げやフライドポテトも食べちゃいけないというわけではないですが、量には気をつけましょう。
アルコールの吸収を遅らせる
アルコールは20%が胃で吸収され、残りの80%が小腸で吸収されると言われています。胃ではアルコールはゆっくりと吸収がされますが、小腸では素早く吸収されるため胃が空っぽの状態でアルコールを摂取すると一気に小腸で吸収され、血中のアルコール濃度が急上昇します。血中アルコール濃度が急上昇するとアルコールの分解が追い付かず、酔いやすくなるほか、肝臓も疲労しやすくなるため他の栄養素の代謝もされにくくなってしまいます。
また、アルコール分解過程で生じる毒物であるアセトアルデヒドの濃度も高くなるため、悪酔いや二日酔いが起きやすくなります。これがすきっ腹にお酒はよくないと言われる理由です。
二日酔いや体脂肪の増加を防ぐためには、アルコールの吸収を緩やかにして、胃に何か入れてから飲むようにすることが大切です。特に、油分やたんぱく質、野菜を先に摂るのが効果的で、食品では豆乳、枝豆、だし巻き、たまご、チーズ、サラダ、カルパッチョ、オクラなどが特におすすめです。
アルコール代謝を促す
アルコールを摂取すると代謝するのに大量のビタミンやその他の栄養素が消費されます。これらを補い、アルコール代謝を促すために必要な栄養素は、ビタミンB群(特にビタミンB1とナイアシン)、ビタミンC、タウリンなどがあります。特にビタミンB₁は大量に消費され、不足すると糖代謝が悪くなるので、燃焼力が低下する原因になります。
居酒屋などのメニューのなかで、これらのビタミンが豊富なおすすめなのは以下の食品です。
- ビタミンB₁:豚肉(なるべく赤身)、玄米、たらこ、枝豆、ゴマ
- タウリン:刺身、あさり、牡蠣
- ナイアシン:ナッツ類
- ビタミンC:レモン、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、カボチャ
食事から必要量摂るのは難しい場合も多いので、飲み会の前後にサプリメントで補うというのも一つの方法です。
水分を意識的に摂る
アルコールを摂取すると、利尿作用により脱水状態になりやすいため積極的な水分摂取が必要です。食事の内容によっては、熱中症による脱水のときと同様に、スポーツドリンクで水分補給するのが良い場合もあります。ただし糖質も多いので、糖質をしっかりと摂った場合にはダイエットを考えるとおすすめできません。
飲酒時は同等量の水分摂取が必要とも言われています。酔いたい時や雰囲気的にお酒以外頼みにくいといったこともあると思いますが、飲酒後はできるだけ早いタイミングで水分を摂るのがおすすめです。水が一番ですが苦手な方は麦茶やウーロン茶、緑茶でもOKです。冷たいものを一気に飲むと消化不良にもつながるため、少しずつこまめに飲むようにしましょう。
まとめ
お酒はダイエット中でも正しく適正量飲むのであれば楽しむことができます。お酒の選び方とおつまみの選び方を工夫して、ストレスを溜めすぎないようにうまく付き合っていきましょう。
あわせて読みたい
 初回体験キャンペーン一覧
初回体験キャンペーン一覧